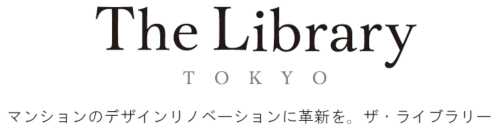横浜H邸プロジェクトは、無事お客さまとの工事契約も締結し、工事着工が見えてきました。ここまで約1年間のお打合せが続きましたが、いよいよ工事を進める段階へとシフトしました。

本体工事の契約の前に、既に別契約で解体工事を終わらせている現場で、墨出しの確認を致しました。「墨出し」とは建築用語ですが、真っ新な土地に建てる新築住宅であれば、設計図面に基づいて壁を立てる位置を現場に墨(またはレーザー)で記していく作業を意味しますが、既存躯体があるマンションでは、既存の壁や柱位置と、解体前に設計していた図面の整合性をとる作業を指すので、少々考え方が違っています。
作業は各務と田口と担当の岸本、そして現場監督の栗原の4人で行いました。

まずはこちらが設計側で用意した墨出し用の平面資料です。ここに書いてあるのは、基準となる線がどこで考えているのか、そこからどれだけの寸法が必要かという考えを示した図面です。

こちらは最初の図面の補足資料となりますが、基準となる線がコンクリートの躯体からどのように求められているかを示しています。仕上げとなる石膏ボードとその下地のLGS(軽量鉄骨)を躯体に対してどのように立てて、どの寸法のものを使うかの考えを書いた図面で、こちらについては、事前に田口と栗原とすり合わせをしております。

事前に現場に入ってくれていた栗原が部屋の中央に取ったX軸とY軸の基準墨の交点にレーザー墨出し機を据えて、そこから基準線の位置を出していきます。
実はマンションの躯体でも直角(建築用語ではカネ)がずれていたり、壁と壁が並行ではなかったり、床が水平(建築用語ではロク)では無かったり、床から壁や柱が垂直(建築用語ではタチ)になっていなかったりするので、まずは部屋の中央に基準墨を出して、そこから墨出しをしてゆくのです。

レーザー墨出し機はこのようなもので、緑色の小型ロボットのようなものが本体となり、手前の黒い機器が受光機となります。3本脚で経っている墨出し機の下部に小さな赤い光が見えるでしょうか?これを基準墨の交点にピタリと合わせて、手前に見ている緑色のレーザー光を基準墨に合わせると、それに直行したレーザー光が出る仕組みとなっています。以前は、本体をレベル(水平)に据えるのも水泡を使った水準器を使って目視で調整していましたが、今はオートレベラーと言って、機械に内蔵された電子気泡管センサーで水平を自動に調整してくれるスグレ物なのです。
まだ、マンションリノベーション設計に特化する前、戸建て住宅も設計していた頃(20年近く前です…)は、差し金(大きな直角定規)や3:4:5の寸法で木の棒で組んだ大きな直角三角形定規、脚立に登った人がおもり付きの下げ振りを使って、2人掛かりで墨出しをしていたことをよく覚えていますが、今はそれに比べる本当に正確に、スピーディーにかつ楽になりました。

レーザー基準機に加えて、田口が持っているレーザー測量器(レーザー光線で距離を測る機器)も小型化して、安価になってきたので、こちらも使えば長い距離も巻き尺で2人掛かりで測っていたものが1人であっという間に測れて、便利になりました。

自然光が入りにくい位場所の方が実はレーザー基準機は使いやすいのですが、奥まった個所の浴室を設置する箇所の壁の直角度合い(タチ)を確認している様子です。床にレーザーの十文字が照射されているだけでなく、壁にも天井にも照射されているのが良く分かりますね。

隣接住戸との耐火二重壁になっている間仕切壁と躯体に対して断熱材(薄緑色のモワモワした部分)が吹かれた手前にLGSが立てられている箇所では、どちらを基準に考えるかによって内寸が変わってくるので、方針を相談しています。

このように実測しながら、相談しながら測った寸法を図面に描き込みながら、これから工事を進めてゆくうえで何が問題になるのかを打ち合わせをしていきます。

一通りの実測が終わって、一応設備関係の配管やダクトのルートを確認して回りました。

奥まった部分に浴室と洗面とトイレと洗濯機が集中しています。灰色の太めの管が各箇所からの排水管となっています。新しいレイアウトでもそれらは大きくは変わっていないので、排水の水勾配は問題なさそうです。給水と給湯管はほぼ最新式のエルメックス管、追い焚き用の二重管ペアチューブも最新式であることを確認しています。

天井裏にはダクト類と電気配線、そしてスプリンクラーのヘッダーが設置されていました。ダクト類についてはやり直し工事がそれなりに発生しますが、概ね問題がなさそうです。天井隠蔽型で設置する予定のエアコンのドレイン管の勾配だけ、何か所か工夫をしないとうまく出来ないことが判りました。

一通りの調査が終わったところで、田口が携帯電話の「LiDAR(ライダー)」を使って、スケルトン状態のお部屋を3Dスキャンしてくれました。ライダーは携帯電話から赤外線レーザーを照射して、対象物まで距離や形状を測量できる技術ですが、それを利用して3次元データを作製することができるのです。

こちらがLiDARで作った3D画像です。今もこのデータから大まかな寸法を拾うことができますが、今後はこのLiDAR技術で現場の詳細な実測が数分でできるようになりそうですね。

測量データを事務所に持ち帰って岸本が作成してくれた正確な実測図がこちらです。これをもとにオーダーユニットバスとオーダーキッチン、そしてそれらに絡んでくる大理石の石工事の製作図を早急に作成依頼することになります。